グローバル経営幹部育成の
「いま」と、日本企業への提言
世界的ビジネススクールからの洞察
高津 尚志
2019年1月25日
事業活動のグローバル化を進める各国の先進企業が、それを担う経営幹部人材、いわゆるグローバルリーダーの確保・育成に強い関心を持ち、切磋琢磨している。一方、日本の人材競争力はIMD世界人材調査で対象63か国中31位に甘んじるなど、心許ない。国際経験豊富で有能な上級管理職が不足する中、外国人高度人材に対する魅力に欠け、経営者教育も不十分、との分析である。しかし、日本企業の対応は、質・量ともに不十分であると言わざるを得ない。
幹部育成を担うチーム自体のグローバル化と知識武装による発想の転換、育成対象と内容の再検討や高度化、英語コミュニケーション能力の徹底的強化などの戦略の立案と遂行が急務である。そして、世界の幹部育成の最先端で進む動き、すなわち学習・事業インパクトの同時希求、行動変容メソッドの導入、経営者候補だけでなく経営者そのものの学習と自己変革に関する先端的な手法の活用、デジタルビジネス変革への対応などに、大胆に取り組んでいく必要があろう。
はじめに
IMDは、経営幹部教育(executive education)において世界トップクラスのランキングを誇るビジネススクールである。もともとネスレが運営していたビジネススクールが、スイスの別の企業系ビジネススクールと合併、1990年に発足した。出自からして、企業経営幹部育成を目的としてきた。
私は、2010年にIMD日本代表に就任して以来、多くの日本企業のグローバル経営幹部およびその候補の育成に関与してきた。幸い、多くの企業の信頼を獲得し、IMDの日本の本領域での存在感は数多ある海外ビジネススクールの中で突出している。
しかし、この間、IMDおよび諸外国の先進企業の経営幹部教育が著しい変化と進化を遂げてきたのに対し、残念ながら全体的に見れば日本企業の変化は不十分である。その差は開く傾向にあり、このままでは厳しいグローバル経営環境の中で日本企業の苦境がさらに続く可能性がある。
まずは、IMDから見た「経営幹部教育」のこの7年間の変化・進化に関し、特に日本企業の実践とのギャップの大きい部分を中心に論じたい。次いでIMDの世界人材調査をベースに、人材に関する日本のマクロレベルでの課題を記す。追って、経営幹部人材、なかんずくグローバル経営幹部人材育成に関しての、日本企業に対する提言を試みたいと思う。
Ⅰ世界の経営幹部育成の進化:IMDからの洞察
グローバルリーダーの定義から始める
IMDでは、2012年に学長ドミニク・テュルパン(Dominique V. Turpin)のもと、自らのビジョンを「成功するグローバルリーダー(個人、チーム、組織)の開発支援において、世界最善になること」と定めた。
あわせて、グローバルリーダーを定義した。
- 現在と未来の複雑で不確かな環境において、組織の変革の旅路を形作り、導くのがグローバルリーダーである。
ここでは、「VUCA World」としての、今日のグローバル経済社会に関する認識と、変革人材としてのグローバルリーダー像が顕著だ。では、より具体的に、グローバルリーダーは何をするのか。
- 複雑性と不確実性の海で舵をとり、いくつもの境界を越えて様々なステークホルダーを成功裏に結束させる。
- その境界には、地理的なもの、機能のサイロ、業界の壁や組織の違いがある。
- そして、組織の変革を実現し、優れた、持続的なビジネスの成果を達成する。
グローバルリーダーが越えるべき境界が「いくつも」示されていることに注目されたい。日本では、国、言語、各国文化の違いなど、主に「地理的な」境界が想起されがちだ。島国日本の企業にとって、これらは確かに大きな境界である。しかし、今世紀に入り、まさに機能・業界・組織の壁を超える形での提携・協業を通じた新たな事業モデルやサプライチェーンの構築が企業の盛衰を左右するようになってきた。デジタル技術の進歩・普及はその傾向をさらに強めている。
グローバルリーダーをどう育てるか
では、かかるリーダーを、IMDはどう育てるか。
- 完全な情報も、簡単な答えも、明らかな解決策もない不快適な状況においても心地よくいられるように。
- 組織の変革の旅路を形作るのに必要な能力を築き、強める。戦略的方針を設定し、戦略を行動に落とし込み、組織の内外のステークホルダーを結束できるように。
- 組織の変革の旅路を導くのに必要な確固たる自己認識を育む。
最初の文章の「不快適な状況においても心地よくいられる」は「become comfortable with the discomfort of...」の拙訳だ。IMDでは「自分の快適域(comfort zone)の外に出なさい」ということを参加者に求める。「グローバル」とは、本質的に自らの快適域の外に出ることを意味するからだ。
次の「必要な能力」には、戦略、組織、マーケティング、財務、イノベーションなどの知識とその運用能力が含まれる。ただ、単なる知識の習得ではなく、「組織の変革の旅路を形作る(shaping organizational transformation journeys)」ことへの適用を重視する。IMDのプログラムでは、参加幹部は具体的に取り組んでいる(または取り組むべき)事業上の課題やプロジェクトを明確にしたうえで、いかにそれを効果的・効率的に解決・遂行できるか、深く具体的かつ多角的に考察することを求められるし、教室内外でのセッションや他の参加者との議論からの学びも、課題解決やプロジェクト遂行への示唆に落とし込むよう指導される。
最後の「自己認識を育む(help them develop a strong sense of themselves)」であるが、リーダーシップに関する世界的な研究の蓄積からは、リーダーとして長年成果を出し続ける人物の多くが、深い「自己認識(self-awareness)」を基盤に、環境や文脈を適切に把握したうえで自らの行動を変容・管理し続けている、ということが明らかになっており、そのことを示すものである。
グローバルリーダーの定義と育成アプローチを明確化したことが、その後IMDのカリキュラムやプログラム設計、提供の思想的基盤となった。私も、これを日本企業との議論に活用してきた。よくできた定義であり、顧客の納得性も高く、顧客の考えが及んでいなかった部分も含めて語られているため、議論を深め、高め、広げることに大いに寄与した。
より多くの日本企業が、「わが社にはどのようなリーダーが必要か」という議論を、単なるコンピテンシーの羅列を超えた一塊の一貫性を持つ文章、一連の行動として定義する、という演習に取り組むべきだと私は考える。その演習なしに育成方法や研修内容の議論を始めることは、本質的に不毛ではないか。
企業・事業へのインパクトの希求へ
2017年1月に新学長にジャン-フランソワ・マンゾーニ(Jean-François Manzoni)が就任すると、IMDはミッションをさらに進化させ、「リーダーを育てる。組織を変革する。あなたの未来に、インパクトを与える」と定めた。前述の思想的基盤に依拠しつつ、より「変革」「インパクト」に力点を置く姿勢が、簡潔に表現されている。
図1を参照されたい。横軸は「Learning Impact(学習インパクト)」、縦軸は「Business Impact(事業インパクト)」である。これは、ビジネススクールとしてのIMDが、何を選び、何を捨てるのか、という戦略の地図であり、他の教育機関・研修会社、あるいはコンサルティングファームとは異なる価値を提供するのだ、という宣言でもある。
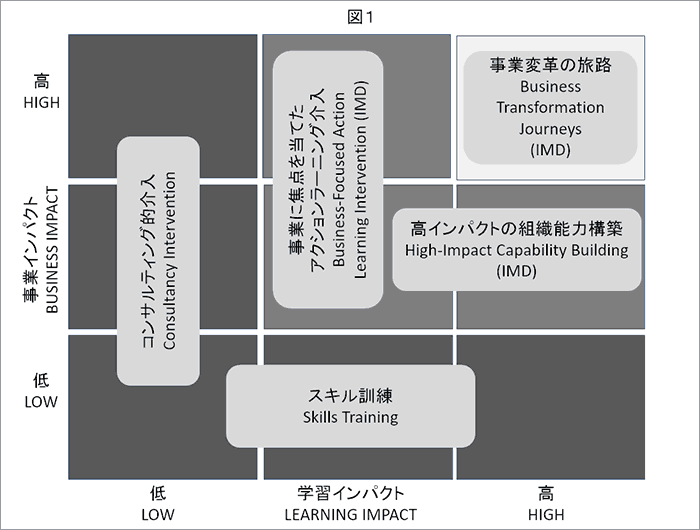
IMDが取り組むのは、学習インパクトと事業インパクトの両方を一定以上の水準で提供できる仕事である。そして、より学習インパクトに重きをおくものを「高インパクトの組織能力構築」、より事業インパクトに重きをおくものを「事業に焦点を当てたアクションラーニング介入」、さらに、両方のインパクトを最高次で追求するものを「事業変革の旅路」と名付けている。
つまり、「ひとを育てる、結果として変革が起こる」というロジックだけでなく、「変革を起こす、その中でひとも育つ」というロジックをも重視するようになった、ということだ。
これは、世界的なビジネス環境の変化と、それに伴う企業顧客のニーズの変化に対応するものでもある。「人材育成」自体は本来長期的な営みであり、長い目での取り組みは大切である。一方、企業変革・事業変革は急務であり、悠長に時間はかけられない。変革に必要な知識や枠組みをいかに短期間で組織内に持ち込み、展開するか。組織の個別具体的な状況とつなげ、必要な行動の定義と実践に取り組むか。そして実際に変革を起こすか。
世界の先進企業の、事業・学習両方へのインパクトの同時希求への要請が高まっており、「事業変革の旅路(Business transformation journeys)」の形でIMDが対応するケースが増えている。これは同一企業内でグローバルに数十人から数百人を巻き込み、数か月から数年にわたって展開する施策に発展するケースが多く、当然CEOレベルの強いコミットメントと、人事・事業・経営企画などのリーダー層の強い連携なしには成立しない。
行動変容に関する科学の進歩を取り込む
2015年にIMD教授シュロモ・ベンハー(Shlomo Ben-Hur)は、『Changing Employee Behavior(従業員の行動を変容する)』という書籍とコンセプトを発表した(Nik Kinleyと共著、邦訳版は未発売)。企業内学習(Corporate Learning)は本来、業績にインパクトを与えるような従業員の行動変容を目標とすべきである、という同教授の主張は、前著『The Business of Corporate Learning』(邦訳版は『企業内学習入門〜戦略なき人材育成を超えて』、高津訳、英治出版)でも明らかだったが、新著ではさらにこの議論を推し進め、心理学、脳科学、行動経済学など近年著しく進歩した領域の知見も借りながら、マネジャーによる従業員の行動変容の方法論を実践的かつ学究的に展開している。
ベンハー教授らの主張を以下に紹介する。
- 人材開発が成果を生むには、「研修・ワークショップ・コーチングなどの個別介入の質」以上に「文脈的諸要素」が肝要。
- 「文脈的諸要素」には「職場(教室外)で起こること」と「個人の中で起こること(意思や自信の水準)」の両方が含まれる。
- 「文脈」の多くは通常のコントロールの範囲外。文脈のうち「何が大事か」、「何に焦点を当てるべきか」を研究、4つの要素を特定。
- 4つの要素それぞれに科学的根拠と、実証された容易な適用テクニックがあり、行動変容へのリアルなインパクトが期待できる。
その4つの要素をまとめた「行動変容に向けたMAPSモデル」を図示する(図2)。
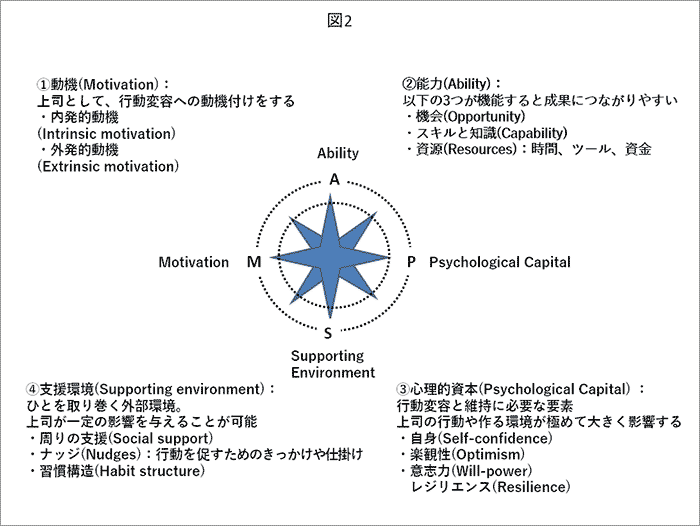
元々、マネジャーによる従業員の行動変容の方法論としての枠組みではある。しかし、教育投資を行動変容として結実させるべく、本人、人事・人材開発部門、部門や上司、企画部門などが境界を越えて連携し、統合的なアプローチを構想、実践するための枠組みとしての援用にも耐えるものだ。
CEOの学習と自己変革も探求や施策の対象に
2017年にIMD教授ベン・ブライアント(Ben Bryant)を中心に、IMDに「CEO Learning Center」が発足した。ブライアント教授は、「変革は不可避であり、変革を可能にするのはリーダーシップである。学習は他の人々がすべきこと、と考えるリーダーは、歴史を作ることはできない」と論じている。センターの趣意書が雄弁であり、訳出する。
- CEOラーニングセンターは、CEOやシニアエグゼクティブの学習能力の探求、理解と開発を目標とする。センターは、リーダーが対等者たち(peers)との非公開(confidential)なコミュニティの中で、自らの諸経験からの深い学びを見出す安全な場(safe place)をつくる。センターの使命は、CEOが組織と自分自身を変革することを手助けすることである。
ブライアント教授は以下のように主張する。
- 幹部の成長のための学びの7割が「役割の中での経験」、2割が「コーチング」、1割が「研修」に起因する、と主張する「70:20:10のルール」はよく知られている。しかし「経験からどう効果的に学ぶのか」に関する関心は、これまで驚くほど低かった。
- 「知識獲得」と「発見と探索(discovery & exploration)」に分けて学習を論じるべき。このうち、後者がより難度が高い。
- 地位上昇に伴い、学習は「普遍的真実」から「文脈具体性」に移り、他社・他者の過去の事例(ケーススタディ)からの学び、一般的法則や経験則の有用性が減少する。他方、自らの経験は豊富で、ここからの「発見と探索」をユニークで豊かな学習資源と考えるのが合理的。
- 経験から学ぶ上では、「感情が邪魔をしうる」ことの認識と対策が必要。成功体験は自尊心をくすぐり、かつてのやり方の繰り返しにつながりがち。失敗は、自尊心を保つために単純化され、他責として解釈されがち。
地位上昇は、学習と成長への寛容性低下に繋がりやすい。「答えをすでに知っている」と周りから期待され、本人もその期待に応えたいと思うからだ。実際に、日本企業の人材育成の責任者から「執行役員以上は、もうすでに必要な学びは終わっていて、かつ、必要があれば自分で学ぶ、ということになっています」という発言を聞く。「ということになっています」というのは、興味深い表現である。
昨今の多くの日本企業の苦境は、従業員の努力やエンジニアの力量の問題ではなく、経営人材、特にトップの経営能力不足に起因している。「経営者候補」の育成には一定の熱心さを持つものの、「経営者」の学習・教育・啓発の促進に取り組んでいる日本企業は極めて少ないのが現実であり、今後、適切な知見の導入と取り組みが求められよう。
デジタルビジネス変革という地殻変動への対応
デジタルビジネス変革への日本企業の関心は、この1年ほどの間に急速に高まっている。ある外資系コンサルティングファームでは、日本の顧客企業に対するプロジェクトの約半数が、なんらかの形でこのテーマに絡んでいるという。一方で、人材育成部門のこれに対する関心や危機感は、企業間較差はあるが、おしなべて低い。デジタルビジネス変革の本質が、技術変革である以上に戦略・組織・文化・人材・リーダーシップや行動の在り方の変革であることを鑑みれば、懸念すべき事態である。
IMDではこれに先んじ、「Global Center for Digital Business Transformation(通称DBTセンター)」を2015年に米シスコ社と共同で設立した。デジタル、つまり技術進歩が可能にした未曽有の「つながり(Connectivity)」が企業にどのような影響を与えるか、その中で特に既存企業がどのような対応をしていくべきか。それを調査研究に基づき論じるための研究センターである。同センターの最初の書籍『Digital Vortex』の邦訳が、『対デジタル・ディスラプター戦略〜既存企業の戦い方』(日本経済新聞出版社)として2017年10月に刊行されているので、ご参照いただきたい。
すでに、今後の組織に必要となる「デジタルビジネス・アジリティ(Digital Business Agility)」、非デジタル時代とデジタル時代のリーダーの要件の違いを抽出した「アジャイル・リーダーシップ(Agile Leadership)」などの枠組みなどが提案され、企業活動や人材育成の現場で活用され始めている。
IMDでは現在、同センターの洞察も活用しながら、デジタルビジネス変革に関連する約10種類の公開短期プログラムを提供している。旗艦プログラムであるLDBT(Leading Digital Business Transformation)という5日間の研修は、年に4回から6回、スイスとシンガポールで開催されているが、毎回50〜60名の定員に対してキャンセル待ちが生じる人気を博している。それだけ、世界各国の企業・企業幹部の関心が高い。
これに参加をした日本人はまだ少ない。人材育成部門のアジェンダにこのテーマが含まれていない、事業・企画部門の認知が低い、語学力の壁がある、といった背景がありそうだ。ただ、グーグルの日本の事業部長や、博報堂の経営企画幹部らが参加をし、内容の有用性や各国の参加者との議論に大きな手ごたえを報告している。また、IMDは日本のコンソーシアム「デジタルビジネス・イノベーションセンター」と提携し、IMD教授がLDBTの内容の主要部分を日本で同時通訳付きで提供することを2016年に開始しており、参加者・参加企業の高い評価を得ている。事業と学習インパクトの両方を希求する取り組みとして、今後日本企業の活用がさらに増えることを期待したい。
また、欧州の保険会社、銀行などは、全社レベルでこのテーマに関する幹部の教育をIMDとともに行っている。日本企業でも、三菱UFJフィナンシャルグループや住友商事などが、IMDとのカスタマイズプログラムの中で、デジタルビジネス変革のセッションを増やすなど対応が進んでいる。
多様な教育手法の組み合わせが進む
日本では、「ビジネススクール=ケーススタディ」という認識が強い。確かに、経営の重要な岐路に立つ主人公の立場で考え、「自分だったら、なぜ、どのように判断し行動するか」を、議論を通じて深く掘り下げて行くケーススタディは、経営者育成のひとつの重要な手法ではある。しかし、IMDなどの先進的ビジネススクール、特に経営幹部教育分野においては、ケーススタディは「多様な教育手法(pedagogies)のうちのひとつ」という位置づけである。そのことは、先述したブライアント教授の考え方からも、ご理解いただけよう。
公開短期プログラムにせよ、企業特化型カスタマイズプログラムにせよ、ビジネススクールの「腕の見せ所」は、プログラムの目的・目標に応じ、どのような内容を、どのような手法・順序・間隔・構成で提供していくか、という全体の「流れ」の設計になった。コーチング、アセスメント、シミュレーション、デザイン思考、俳優とのコミュニケーション演習、オンライン学習、アクションラーニングなど様々な教育手法の最適な組み合わせ、である。顧客側も、教育機関との共創的議論を通じて、納得できる「流れ」をともに作っていくことを心がけるのがよいだろう。
Ⅱグローバル人材活用に苦しむ日本
世界人材調査2017に見る、日本の課題
IMDが毎年5月に発表する世界競争力ランキング(World Competitiveness Ranking)は、世界的に注目を集めている。富を生み出す各国の力に関する国際的な比較で日本は、1980年代終盤から90年代初頭に世界第1位であったが、最新の2016年版では調査対象61か国中26位に沈んでいる。原因は、「国際化からグローバル化へ」「アナログからデジタルへ」「ものづくりからイノベーションへ」といった世界規模の変化への適応不全にあると言えよう。
同調査を担当するIMDの世界競争力センター(IMD World Competitiveness Center)は、世界人材調査(World Talent Report)の集計と発表も行っている。各国のパフォーマンスを、人材に対する「投資と開発」、人材をひきつけ、維持する「魅力」、現時点での人材面における「準備度」という3つの大きなカテゴリーから測るものである。
2017年11月発表の最新ランキングで、日本は調査対象63か国中31位という憂慮すべき位置に甘んじた。調査からは、相変わらず環境変化に対する適応不全に苦しむ、日本の課題がくっきりと見えてくる。
- 「従業員への訓練を重視する度合い」では世界5位であるが、「経営者・管理者教育のビジネス経済ニーズの充足度」では53位。
- 「有能な上級管理職の十分な供給」で58位、「上級管理職レベルの国際経験の十分さ」では63位(調査対象国中最低)。
- 「語学力の企業ニーズの充足度」では59位。
- 「外国人高度人材への魅力」では51位で、アジアで最低。
人材競争力が国の総合的競争力の先行指標であろうことを鑑みれば、憂慮すべき結果である。グローバルな事業で成果を出すためには、グローバルな経営人材の特定・獲得と育成・活用に関して、包括的で大胆な施策の構築と実施が急務であろう。
Ⅲ日本企業への提言:グローバルでデジタルな時代に「勝つ」ために
さて、まとめに入りたい。世界人材調査では、日本の極めて厳しい現実を見た。企業は、あらためて自分の言葉でグローバル経営幹部像を定義し、その特定・獲得と育成・活用に関し、戦略的に取り組む必要がある。事業と学習インパクトのバランスのとれた希求、行動変容の方法論の導入、CEOなどトップ層に対する根拠のある学習施策、デジタルビジネス改革への取り組みが求められる。また、教育手法が多様化する中、その効果的な組み合わせと流れの設計が肝心であることも記した。
最後に、この戦略の策定と実行の前提となりうる、3つの提言を行いたい。
幹部育成チームこそ、グローバルリーダーたれ
先に、グローバルリーダーとは「組織の変革の旅路を形作り、導く」ものであり、いくつもの境界を超えるものであることを論じた。幹部育成施策を設計し、運営する責任者、担当者とチーム自身が「グローバルリーダー」として行動しなければ、グローバル経営幹部の育成などできない。たとえば、以下に取り組んではどうか。
- 「多国籍チームを作る」
日本企業でも海外拠点には人材育成に関する専門的な知識・経験を持つ担当者や責任者が存在することがある。仮に専門知識がないにしても、別の視点・視界をもつ彼らの知見を活かすことはバランスの取れた施策構築と運営に有効である。彼らとの作業を通じて、チーム自体がグローバルを経験できる。本部にいる日本人だけでチームを編成すると、様々なバイアスが生じやすい。- 対象者バイアス:日本人中心になったり、日本人が好む外国人になったりする。
- 育成手法バイアス:理念浸透、企業文化、教養教育などの「ソフト」イシューに偏りがち。修羅場を作る、過度な課題を与える、とにかく厳しく、といった「タフ」アプローチに偏りがち。
- 「専門的知見を得る」
大半の日本企業の人事部門には、頻繁な異動により、人材育成に関する知見の蓄積がない。また、教育はもともと持論で語られやすい。かつ、日本企業は日本企業同士のベンチマークに終始しがちだ。したがって育成手法バイアスや、危険な運用(育成と選抜の二兎の無分別な追求、無資格者をコーチに任命、など)が発生しやすい。
若干我田引水になるが以下をお勧めする。- 書籍『企業内学習入門』を活用:企業内学習の戦略や施策の策定、ブランディング、ガバナンスなどを包括的に学べる教科書として。
- IMDの「Organizational Learning in Action (OLA)」を活用:ベンハー教授による、企業内学習に完全特化した5日間の研修である。世界の企業の人材開発(HRD)、組織開発(OD)などの幹部が集い、ともに学ぶ。世界的動向、最新の知見を学び、自社の育成戦略に生かす。
- 「社内で部門を超えて連携する」
日本企業では、幹部教育は人事部主導で学習インパクトを偏重する中、少人数・散発的な取り組みになりがちだ。参加者本人が気づきやきっかけを得ても、それを「知識や枠組みを持ち込む」「展開する」といった組織的な動きにすることは、本人だけの努力では難しい。一方、経営企画部などは事業インパクトの希求に専心する中、育成的アプローチが持つ力を見落としがちだ。トップ層への施策は、社長室等の関与なしには難しいだろう。機能の境界を超えて連携し、事業・学習両方のインパクトの同時希求を目指す動きが増えることに期待したい。
CEO・執行役員レベル、取締役の教育に投資せよ
有力企業では、トップ層の知識の獲得にはさして課題を感じていないはずだ。本社にいても、コンサルタント、学者、または経営企画部がレクチャーしてくれる。難しいのは、知識を洞察に変えて自分・自社への示唆に落とし込む部分(時間が必要)、世界の動きに関し間接情報ではない情報を得ること(機会が必要)、自らの豊かな経験を、自分・自社の変革のための学びに変えること(方法論が必要)、の3つであろう。例えばIMDでは、以下のような場や拠点を用意している。
- CEO円卓会議(CEO Roundtable)
世界各国の優良企業のCEO数十名が足掛け2日間、IMDに集う。テーマ(2017年は「デジタルビジネス」、18年は「CEOの学習」を予定)を定め、IMD教授の講義、参加CEO代表数名による短時間の発表などを素材に議論。メディアも随伴者もいない、エクスクルーシブな学習と交流の場である。同様のフォーマットでCDO(Chief Digital Officer)、CLO(Learning)、CMO(Marketing)などの円卓会議も開催している。 - CEO Learning Center
これについては前述したが、すでにウェブサイト上でも論考を公開している。また、今後、このセンターの方法論に依拠した、CEOを対象としたプログラムの提供も予定している。 - High Performance Boards
日本でもガバナンス改革が盛んだが、今後、ボードの質(人材、情報、プロセス、力学などの適切なマネジメント)が企業の盛衰を左右する場面が増える。「IMD Global Board Center」では40年にわたる研究を基盤に、世界中のボードに教育やコンサルティングを提供している。HPBは、世界の諸企業から集まる取締役とともに学ぶ公開短期プログラムである。
英語コミュニケーションスキルを徹底的に鍛えよ
グローバルなビジネスの文脈で経営幹部を目指す人材にとっては、英語での十分なコミュニケーション能力はもはや不可欠である。本社に各国から集う各国幹部との、戦略や方針に関する議論。解雇や契約解消といった厳しい場面での対話。異国の従業員を鼓舞する演説。日本語に訳されている情報(当然日本のメディアなどのバイアスがかかっている)以外の情報から学ぶこと。いずれにおいても、読み書き、プレゼンテーション、議論、対話、すべてに関し一定水準の力が必要だ。
激しい議論でも冷静に自らの考えを表明できる語学力と胆力、対話の中から解を見出すファシリテーション能力、問いを通じて相手の考えを深め、行動を促すコーチングスキルも、有用である。
これまでの日本の学校制度での英語コミュニケーションスキル教育は、ほぼ完璧な失敗であり、国難と言っていい。近年、一部の中学、高校や大学で野心的な取り組みが開始されたことは歓迎すべきだが、その生徒や学生がビジネスの世界で活躍するまでにはタイムラグもある。企業は、現実を直視し、これからの時代の経営幹部人材に必要なスキルを特定し、その開発に投資すべきだ。
IMDのような海外トップスクールができることは、ある程度の基礎力と意欲がある人材に、更なるインパクトを提供することで、グローバルリーダー、グローバル経営幹部としての成長を支援することである。基礎力と意欲に関しては、企業における担保が前提となる。
拙稿が各企業のグローバル経営幹部育成の質量の充実に向けた一つの素材となることを願い、読者諸氏との議論を待つこととしたい。
[参考文献]
ドミニク・テュルパン、高津尚志(2012)『なぜ、日本企業は「グローバル化」でつまずくのか─世界の先進企業に学ぶリーダー育成法』(日本経済新聞出版社)
ドミニク・テュルパン、高津尚志(2015)『ふたたび世界で勝つために─グローバルリーダーの条件』(日本経済新聞出版社)
シュロモ・ベンハー(2014)『企業内学習入門──戦略なき人材育成を超えて』(高津尚志訳、英治出版)
マイケル・ウェイド他(2016)『対デジタル・ディスラプター戦略─既存企業の戦い方』(根来龍之監訳、日本経済新聞出版社)
高津 尚志
世界経済評論 2018年3月4月号に掲載
